
「せっかく保育士資格や幼稚園教諭免許を取ったのに、どこで働けるのかわからない」「ブランクがあって不安…」そんな声をよく耳にします。
これらの資格は保育所や幼稚園だけでなく、さまざまな場所で活かせる資格です。
今回は、保育士資格・幼稚園免許を持つ方が働ける主な職場や、それぞれの特徴について紹介します。
① 保育所(認可保育所・認可外保育施設)
最も多くの人が働いている場所です。
0歳~就学前の子どもたちを日中預かり、保育・生活支援を行います。
勤務時間はシフト制が多く、早朝~夕方までの交代勤務になります。
特徴:保育士資格が必要、フルタイムだけでなく、パート勤務も可能、公立・私立で待遇や働き方に差がある
② 幼稚園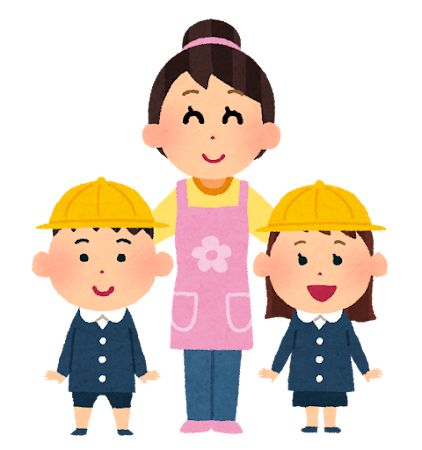
文部科学省の管轄で、3歳~5歳の子どもを対象に教育的な活動を行います。
基本的に「学年制」で、カリキュラムに沿った活動を行う点が保育園との違いです。
特徴:幼稚園教諭免許状が必要(1種・2種)、夏休み・冬休みなど学校と同じような長期休暇がある場合も正社員・契約・非常勤など多様な雇用形態
③ 認定こども園
保育所と幼稚園の両方の役割を持つ施設で、子どもを預かりながら教育も行います。年々施設数が増えており、両方の資格を活かせる場所です。
特徴:保育士資格と幼稚園免許の両方を持っていると有利、子どもの年齢層が幅広い、教育と保育の両方の視点が求められる
◆豆知識◆
保育所は厚生労働省、幼稚園は文部科学省が管轄でした。
縦割り行政の課題を解決するために、2006年に認定こども園制度が創設され、2015年から認定こども園の設置が全国的に普及されました。
〇共働き世帯が増加しているのに、幼稚園は昼までしか預けられない・・・
〇保育所は保護者が就労していないと預けられない・・・
これらの問題を受けて、地域や家庭のニーズに柔軟に対応できる「認定こども園」が誕生しています。
宮崎県では令和6年度時点で150園が認定こども園として運営されています。
さらに認定こども園は運営主体の違いにより4つの形態に分けられます。
1)幼保連携型:幼稚園と保育所の両方の機能を持つ
2)幼稚園型:幼稚園が長時間預かりなどを追加して認定を受けた形
3)保育所型:保育所が教育的な活動(カリキュラム)を強化して認定を受けた形
4)地方裁量型:地方自治体が独自に基準を定めて運営している
2015年以降認定こども園に移行した幼稚園や保育所が多く、認定こども園に移行する前は幼稚園か保育所なのかで園の傾向を判断することが出来ます。
④ 学童保育・放課後児童クラブ
小学生の子どもたちを放課後に預かり、宿題を見たり遊びの支援をしたりします。
保育士資格や幼稚園免許を持っていれば歓迎されるケースが多いです。
特徴:保育士資格があると採用に有利、主に午後~夕方までの勤務、小学生との関わりが中心
⑤ 病院内保育所・企業内保育所
看護師や会社員の子どもを預かる、小規模な保育施設です。
病院や会社の中に設置されており、勤務するスタッフの子どもを預かるケースが多いです。
特徴:少人数の保育が中心、夜間保育がある場合も、保育士資格があれば働ける
⑥児童福祉施設(児童養護施設・乳児院など)
親元で暮らすことができない子どもたちが生活する施設で、日常の世話から心のケアまで幅広い支援が求められます。
深い信頼関係を築くことが大切な仕事です。
特徴:保育士資格が必要、夜勤を含むシフト勤務あり、心理的ケア・対応力も求められる
⑦ ベビーシッター・保育マッチングサービス
個人宅で子どもの世話をする仕事で、保育士資格を持っていると信頼度が高まります。
近年はマッチングアプリやサービスを通じて依頼を受ける働き方も広がっています。
特徴:フリーランス的な働き方も可能、自由なスケジュールで働ける、利用者との信頼関係が重要
⑧ 保育専門学校・子育て支援センターなどの指導・支援職
現場での経験を活かして、次の世代の保育士を育てたり、地域の親子支援を行ったりする仕事もあります。
キャリアアップや再就職後の選択肢として人気です。
特徴:実務経験が重視される、指導や相談業務が中心、子育て支援の知識も役立つ
保育士資格や幼稚園免許は、活かせる場所がたくさんあります。働き方やライフスタイルに合わせて、柔軟に選べるのが大きな魅力です。
ブランクがあっても、短時間勤務や再研修制度を活用すれば、再スタートも十分可能です。
子どもに関わる仕事がしたい、資格を無駄にしたくないという方は、自分に合った職場を探して、資格を活かした働き方を目指してみてはいかがでしょうか?


